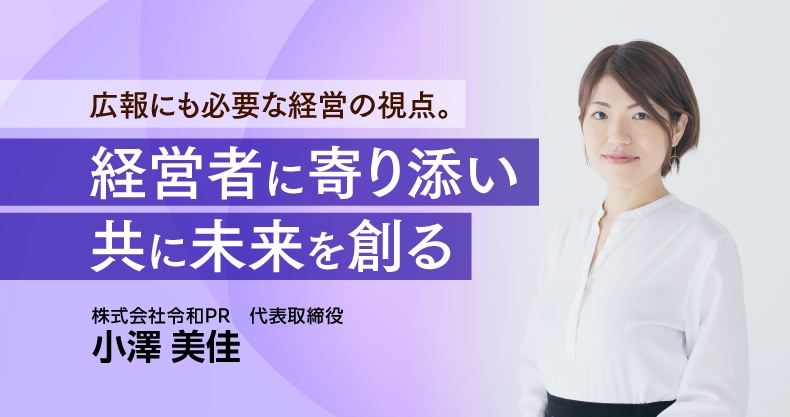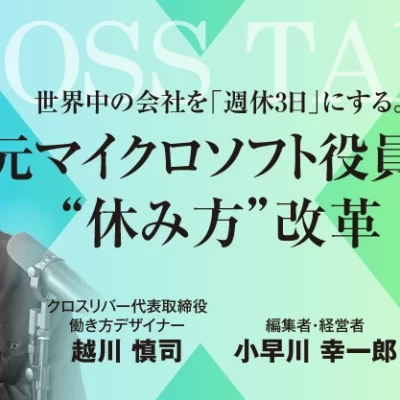昨今は企業がSNSで手軽に情報発信できる時代になりました。しかし、その広報活動は本当に企業に利益をもたらし、経営を前進させているでしょうか。
株式会社ニットで広報を担当しながら、株式会社令和PRの代表を務める小澤美佳氏。自身の経験から「広報も経営視点を持つべきだ」と語ります。PRは単なる情報発信ではなく、経営戦略と密接に結びつくことで、企業の成長を加速させる重要な役割を担います。

小澤 美佳(こざわ・みか)
株式会社令和PR 代表取締役
2008年に(株)リクルートへ入社。中途採用領域の代理店営業、営業マネージャーを経て、リクナビ副編集長として数多くの大学でキャリア・就職支援の講演を実施。採用、評価、育成、組織風土醸成など幅広くHR業務に従事。2018年、中米ベリーズへ移住し現地で観光業の会社を起業。2019年(株)ニットに入社し、営業・人事を経験後、広報部署の立ち上げ。2021年はテレワーク先駆者百選の総務大臣賞やTOKYOテレワークアワードなど数々の受賞を実現。立ち上げ2年でメディア露出数1004件にのぼる。育休中に、兼業で起業。現在はHELP YOUの広報と令和PRの代表の二足の草鞋を履きながら相乗効果を図る。 X(@mica823)のフォロワー数は4.4万人。ポッドキャストやVoicyなどの音声メディアでも広報ノウハウを発信中。
本質的なPRのために経営者の思考を理解する

PRは、すべての企業が行うべきだと思われがちです。しかし、必ずしもそうとは限りません。例えば、弊社に採用目的の広報依頼があり、蓋を開けてみると離職率が高いケースがあります。その場合は、採用活動よりも先に、リテンションのためのインナーブランディングの実施を提案します。離職率が高いという課題を抱えたまま、社外に向けて良い面ばかりを発信してしまうと、実態との乖離が浮き彫りになり、かえって逆効果になる可能性もあるからです。このように「今はPRをすべきではない会社」は存在しています。
しかし、基本的には多くの企業がPRに取り組むべきだとも思っています。ある程度、組織の土台が整ってきた会社は、なるべく早い段階で認知度と信頼性を高める活動をする必要があります。第一想起の獲得やブランディングは、一朝一夕に実現できるものではなく、コツコツと時間をかけて積み上げていくものです。
広報の役割は「中長期的に、会社の第一想起を獲得するための活動」だと考えています。私は企業の広報活動を、よくリンゴの木に例えます。まず「根」は会社の存在意義です。ミッション・ビジョン・バリューや組織文化、これまでの歴史など、揺るがない基盤となるものです。「根」の部分がしっかりしていることを前提として、その上の「幹」となる「第一想起」をどのように築いているかが重要になります。
このように、本質的なPRを行うためには、経営とPRを結びつける必要があります。社長から「メディアに取り上げられるように頑張りなさい」と指示され、広報がようやく取ってきた案件が『ブラック企業特集』だったらどうでしょうか。これは極端な例ですが、会社にとってマイナスになるPRを取ってきてしまうケースは意外に多く存在します。
私自身も、同様の失敗をした経験があります。現在所属している株式会社ニットに、数年前59歳のメンバーが入社しました。ご両親の介護のために2度の離職を経験しており、リモートワークで働きたいとのことでした。「59歳で入社」という事実が話題を呼び、私は意気揚々と、その方への取材依頼を広報としてたくさん受けました。
そんな時、人事担当者から「取材を受けること自体はダメではないけれど、うちはシニアだけを採用している会社ではないのだから、もう少し見せ方を考えてほしい」と指摘されました。
一度特定の切り口で取り上げられ始めると、次々と同様の内容で取材依頼が舞い込み、それが会社のイメージとして広まってしまいます。経営陣がどこを目指しているのか、また、その目標達成のために広報がどのような発信をすべきか。常に点検し続けないと、最初はわずかなズレだったとしても、広がり続けるうちに大きな差を生んでしまう危険性があります。これが広報という仕事の怖さです。
だからこそ、広報担当者から主体的に経営に触れにいくことが重要だと考えています。ベンチャーやスタートアップでは、朝令暮改が日常茶飯事で、社長の方針は頻繁に変わります。また、規模が大きい企業であれば、社長だけでなく、役員を含めた経営陣が存在しています。
社長がどのような本を読んでいるのか、どのような人々と交流しているのか、どのような会合に参加しているのかを知っていく。また、役員がどのような会議に出席しているか把握し、広報も参加する。このように広報が社長や経営陣の考えを深く理解して、経営視点や思考を常にアップデートし続けなければ、変化や心情の機微を正確に読み取ることは難しいと思っています。
しかし経営者でもないのに「経営視点を持て」と言われても、難しいと感じるかもしれません。そんな広報の方は、社長と接することに加えて、営業、人事やマーケティング担当など、周辺の人たちにも触れにいくことが重要です。「経営」という言葉は、企業活動全体の総称です。さまざまな現場に触れることで、多様な感覚を知ることができます。
「リアルな声」が信頼を築く時代

経営視点を持って、広報戦略を立てる上で、現代のメディアを理解することが必要です。メディアは、それぞれの頭文字を取った「PESO」と呼ばれる4種類に分類されると言われています。
・Paid Media:広告費を支払って利用するメディア(例:テレビCM、Web広告など)
・Earned Media:第三者によって情報が発信されるメディア(例:新聞、テレビ、Webメディアの記事など)
・Shared Media:ユーザー間で情報が共有・拡散されるメディア(例:SNS、口コミサイトのレビューなど)
・Owned Media:自社で所有・運営するメディア(例:自社ウェブサイト、ブログなど)
この中で、Shared MediaとOwned Mediaの2つは、企業が自らの言葉で情報を発信できる媒体です。一方で、Earned Mediaは第三者が作成しており、信頼性は高くなります。しかし、必ずしも自分たちが意図した通りの内容になるとは限らず、コントロールが難しいことがあります。
SNSが普及したことで、どのような企業であっても、自分たちが伝えたいことを自由に発信できる時代になりました。さらにSNSでは一方的な情報発信だけでなく、ユーザーとの双方向なコミュニケーションを図ることが可能です。言いたいことを伝えられ、つながりたい人とつながることができる。SNSの台頭は、まさにPRを大きく変化させるきっかけとなりました。
私が代表を務める令和PRも、採用活動はすべてX(旧:Twitter)で行っています。リード獲得やイベント集客も、ほとんどがSNSからです。SNSを通じたコミュニティは、大きな力を持っていると実感しています。
私の大好きな『僕らはSNSでモノを買う(著:飯髙悠太)』という本の中で、「ULSSAS」という造語が紹介されています。これは、自分が好きな人の「リアルな言葉」や口コミに触れて商品やサービスを初めて知り、「それはどんなものだろう?」と探し、「買ってみよう」という行動につながるプロセスを指しています。
ULSSASのUにあたる「UGC(User Generated Content:ユーザー生成コンテンツ)」は、ユーザーの「リアルな声」です。綺麗な髪の芸能人が登場するシャンプーのCMや、インフルエンサーが紹介するPR商品に対して、「どうせ宣伝でしょ?」と多くの人が感じるようになってきています。
商品に限らず、企業も同じです。広報が「うちは良い会社です」と発信しても、「広報はそれが仕事だから」と受け取られてしまう場合もあります。
一方で、営業担当者やマーケティング担当者が同じことを言ったらどうでしょうか。自分の信頼している人間が、会社のことを本音で語っていたら、「本当に良い会社なんだな」と感じるのではないでしょうか。
このように、広報は「UGC」を生み出すための戦略的な広報活動を行う必要があります。例えばイベントを開催したときに、参加者に対して「SNSでハッシュタグをつけて投稿してください」と一言添えるだけでも構いません。UGCが自然に生まれるような仕掛けを考え、取り組むことが重要です。
「私がその夢を実現させます!」

令和PRを立ち上げたきっかけは、より多くの企業の経営を加速させていきたい、という想いが強くなったことです。「経営者の力になり、想いを言語化する手助けをしたい」そう思うようになったきっかけは、二つあります。
一つ目は、私の父方も母方も自営業を営んでいた影響です。経営者の野望と苦悩を、幼い頃から身近で見て育ちました。この経験から、将来はベンチャーやスタートアップ企業の社長の右腕のような存在になりたいと考えるようになり、リクルートに入社しました。
二つ目は、リクルートで代理店営業を担当した経験です。HR領域は景気の影響を受けやすく、潰れてしまう代理店も少なくありませんでした。その時に社長という立場は、覚悟を持ち、社員一人ひとりとその家族の生活をも背負って会社を経営している事実に気づかされました。
1年間、自身の給料はゼロだったけれど、絶対に社員はクビにしないことを決めていた社長。一方で、不景気に持ちこたえられず、涙を流しながら社員に退職を促していた社長。苦しみながらも、実現したい未来に向かって突き進んでいるのが「社長」という存在でした。そんな社長たちの熱い想いに触れ、経営という本業に集中できる環境を作りたい、と強く思うようになりました。
ナショナルクライアントと呼ばれるような日本を代表する企業から、一人経営の企業まで、多種多様な企業の経営者と仕事をさせていただきました。経営者の方々と対等に会話をするためには、自分自身も同じレベルで物事を理解し、考えられるようにならなければならない。そのためには、絶えず学び続ける必要があると思っています。
ニットに入社してからも、「社長の右腕になるぞ」という想いで業務に取り組んできました。代表を務める令和PRにおいても、単なるPR会社ではなく、「経営をPRで加速させる」ことを目指しています。
会社経営は、良い時ばかりではありません。だから、苦しい時こそ寄り添える存在でありたい。利益になるかどうかは一旦置いておき、人を扱うプロフェッショナルとして、お客様と共に走っていきたい。そのような想いで、これまでお客様と向き合ってきました。
社長の熱い想いや言葉に心を揺さぶられた経験は、数え切れません。そのたびに「私がその夢を実現させます!」と言いたくなってしまいます。そうした経験は、今の私の活動にも生きており、これからも大切にしていきたいと思っています。
PRの力であらゆる企業を前進させる

PR業界は今、過渡期にあります。かつてのように「メディアに取り上げてもらう」ことだけが広報の役割ではなく、SNSやオウンドメディアを通じて、企業自らが情報を発信する時代になりました。
「テレビはオワコン」と言われ始めたように(実際にオワコンではないですが)、人々が情報を得る方法は多様化し、可処分時間の使い方も人それぞれに異なっています。予算を持っている大手企業だけでなく、資金力が限られている企業でも認知を拡大し、ファンを獲得することができます。必ずしもすべての人に知られる必要はなく、自分たちがターゲットとする人々に知ってもらい、好きになってもらう。それから、商品を購入してもらったり、採用に応募してもらったりできれば良い。過渡期だからこそ、どんな会社でも、どんな人にとってもPRにできることには可能性が秘められているんです。
しかし、PRに関する情報は世の中にまだ十分に広まっていません。PRを通じて、より多くの企業の世の中での認知獲得を支援する。そして、結果的に経営に貢献できるような活動がしたい、と考えるようになり、起業することを決めました。でも、正直に言うと貢献するための手段は、PRでなくてもいいんです。
HRでも、営業でも、自分が持っている知識やスキルで貢献できることがあれば、何でも構いません。現在はPRという領域で活動していますが、企業が何らかの「武器」を身につけることで、本当に実現したいと願っている世界観に近づくためのサポートができる存在でありたい、と考えています。
私自身、多くの経験豊富な経営者の方々から見れば、まだまだ未熟な部分も多い。常に学び続け、精進していかなければなりません。アンテナを高く張り、情報をインプットしながら、多くの企業の経営を前進させるサポートを続けていきたいです。結果として、世の中がより良くなり、誰もが「幸せだな」と思えるような世界観を、本気で創り上げていきたいと思っています。
編集・取材・文:鬮目真伸(クロスメディア・パブリッシング)