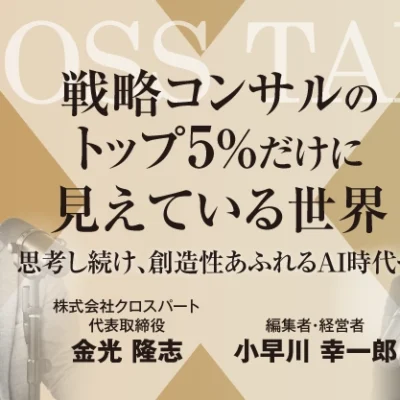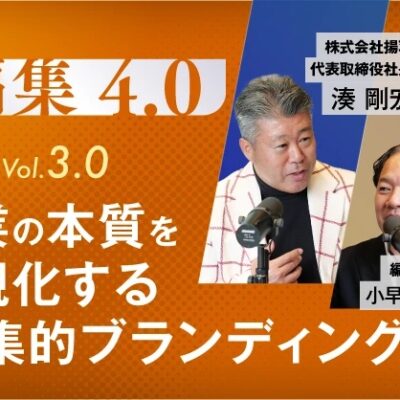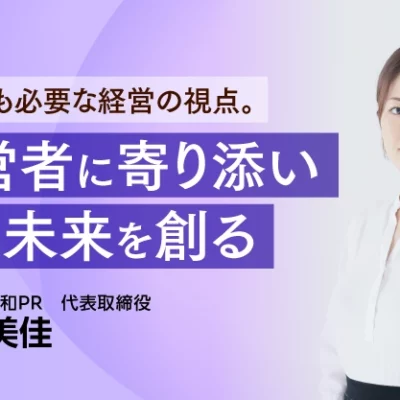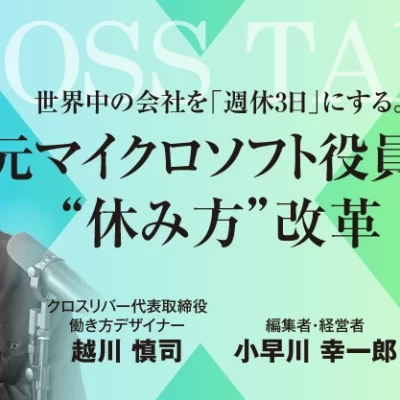PURPOSE
豊かなコミュニケーションを広げ、世界を幸せな驚きで包む。
1997年の創業以来「コミュニケーション」を軸としてビジネスを展開してきたMIXI。スポーツ、ライフスタイル、デジタルエンターテインメントなど徐々に事業領域を拡大。2024年12月に発表された「mixi2」は、わずか10日足らずでユーザー数120万人を突破し話題を呼びました。
2022年にはコーポレートブランドをリニューアルし、パーパス、ミッション、ロゴに至るまで大きなイメージ刷新を図りました。刷新の理由として木村弘毅社長は、MIXIの実態と人々のイメージの「乖離があった」ことを挙げています。
ブランドリニューアルによって、いまMIXIはどのように変化しているのか。リニューアルの背景と、次に目指す姿について、株式会社MIXI代表取締役社長上級執行役員CEOの木村弘毅氏に聞きました。
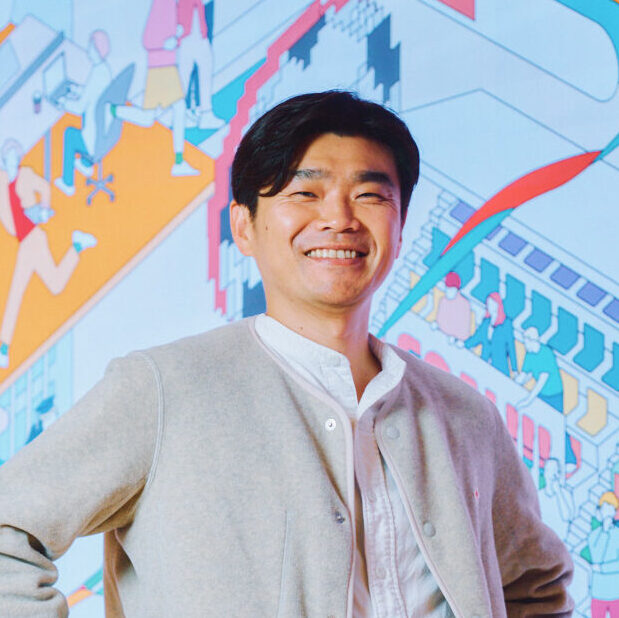
木村 弘毅(きむら・こうき)
株式会社MIXI代表取締役社長 上級執行役員 CEO。電気設備会社、携帯コンテンツ会社等を経て、2008年ミクシィ(現MIXI)に入社。ゲーム事業部にて「サンシャイン牧場」など多くのコミュニケーションゲームの運用コンサルティングを担当。その後、モンスターストライクプロジェクトを立ち上げる。2014年11月執行役員、2015年6月取締役、2018年4月取締役執行役員、2018年6月代表取締役社長執行役員、2020年4月代表取締役社長。2021年3月、早稲田大学大学院スポーツ科学研究科修士号取得。2022年4月、代表取締役社長上級執行役員就任。2023年4月代表取締役社長CEO、2023年12月より現任。
MIXIは、ただの「IT企業」ではない
木村 MIXIが創業以来、一貫して大切にしてきたもの。それは「コミュニケーション」です。
MIXIは、よくIT企業だと言われます。これはMIXIがテクノロジーで評価されているということです。ただ、IT企業と呼ばれる企業は数多くあるなかで、「MIXIだけにしかないバリューとは何か?」を考えなければなりませんでした。
それを説明するために重要なのが「コミュニケーション」への特化だったのです。
経営においては、さまざまなステークホルダーと合意形成を図る必要があります。たとえば、投資家の方々に対し「MIXIが他社と差別化できる強みは何か」「MIXIの事業が永続性を持って続けられる根拠は何か」を示すために“コミュニケーション”が重要になります。
ドッグイヤーでテクノロジーが進化するなか、コミュニケーションも新たなスタイルへとアップデートされ、次の時代へと紡がれていくべきです。私たちはただコミュニケーションを軸として差別化を図っているのではなく、「テクノロジーを武器としたコミュニケーション」に特化してきたからこそ、差別化ができていると言えます。

テクノロジーを活用したコミュニケーションサービスとしては、どんな企業にも負けないものを持っている。そんな自負を持って事業に取り組んでいることを、ステークホルダーの方々に正しく伝えていかなければなりません。だからこそパーパスを通して、MIXIが「コミュニケーション」に注力していることを、あらためて強調してきました。
現社長でも「2度落ちた」
MIXIがコミュニケーション企業であることをパーパスで表現したことは、IRだけでなく採用においても重要な効果を発揮してきました。
いま若手人材は「何のために働くのか」をよく考えています。その問いに対し、企業が明確な「解」を出せなければ、人材獲得が難しい時代になっています。
仕事をする意味の中心軸に、最初から「コミュニケーション」を置いて働いている人は、さほど多くないでしょう。しかし、人々のコミュニケーションを豊かにすることの大切さについて問いかけると、共感する若手人材が非常に多くいます。これは採用における合意形成ができているということです。
たとえば、「モンスターストライク」(モンスト)が爆発的にヒットした時代には、「ゲームをつくりたい」という人が多くいました。それ自体は悪いことではありません。ただ、いまでは「“人と人をつなげるゲーム”をつくりたい」と、MIXIの理念を根底にした仕事に、モチベーションを湧かせてくれている人材が非常に多くなっています。
これはつまり、パーパスという共通言語が、集まるメンバーに同じ方向を向かせてくれているということです。入社前の段階で「MIXIはどんな会社なのか」「自分とマッチしているか」を理解しやすい状況が生まれている。その結果、価値観のミスマッチによる離職は減り、長期的に見てもプラスの変化をもたらしています。
採用時だけでなく、入社後の人材の活躍にも変化が起きています。私たちは2022年にコーポレートブランドをリニューアルしましたが、それによって従業員のコミットメントや、MIXIで働くうえでのロイヤリティが高まっていることが、社内サーベイでも如実に表れているのです。

従業員ばかりでなく、私自身も人とのコミュニケーションが大好きだったことから、2008年にミクシィ(当時)に入社しました。コミュニケーションを主軸にSNSでナンバーワンを取っていたミクシィでどうしても働きたかった。採用試験は2度落ちて、3度目でやっと内定をもらいました。
そんな私が持っていたようなコミュニケーションに懸ける魂から、「モンスト」が生まれ、「家族アルバム みてね」が生まれ、SNS「mixi」に続くさまざまなヒットサービスが誕生してきました。
こうして幾万もの人々のコミュニケーションを生む私たちの存在価値を、顧客、投資家、従業員など多くのステークホルダーに知ってもらう必要があります。その意味でもパーパスは重要であり、組織や事業に大きな変化を生み出してきました。
ホスピタリティの本質
私たちはパーパス実現に向け、「『心もつながる』場と機会の創造。」というミッションを定めています。「心もつながる」は、MIXIの事業展開のうえで非常に重要なテーマです。
たとえば2024年4月には、MIXIと三井不動産との共同事業でプロバスケットボールチーム「千葉ジェッツ」の新ホームアリーナ「LaLa arena TOKYO-BAY(ららアリーナ東京ベイ)」が完成しました。
建設を決めたとき、まず考えたのは「どうすれば、心もつながる場と機会を創れるか」でした。まず私たちサービス提供者のホスピタリティが求められます。来場いただいた方に質の高いホスピタリティを持ってサービス提供するべく、アリーナ全体にさまざまな工夫を施しました。
例を挙げると、千葉ジェッツの試合時は、飲食売店エリアではスタンディング形式で食事をしながら会話ができ、アリーナに迫り出したバルコニールームでは立食パーティーなどができます。VIPルームでは、フレンチのフルコースを楽しみながら、仲間たちと試合観戦をしてワッと盛り上がることができる。試合後には、選手がサインをしてくれたり、みんなで写真撮影ができたりすることもあります。

写真提供:TOKYO-BAYアリーナマネジメント
「写真を撮る」という行為も、ひとつのコミュニケーションです。子どもとスポーツで盛り上がった写真が「みてね」にアップされれば、幸せが拡散されていきます。ゲームもスポーツも、MIXIが展開するサービスすべては、人を幸せにするコミュニケーションのためにあります。
人をおもてなしするとは、心をつなぐ場を提供するということ。つまり、コミュニケーションこそがホスピタリティの本質である。私はそう考えています。
そこに「幸せな驚き」はあるか
スポーツにもすそ野を広げて事業が多角化するなかで、MIXIは、世のなかに何を提供しているのか。そう問われるとき、私たちは「幸せな驚き」であると答えます。
たとえば近年のSNSは、とにかくインプレッションを稼ぐことに比重が置かれています。情報が嘘か本当かは関係なく、炎上して目立つことができればプロモーションとして成功とされる。あるいは、ニュースで取り沙汰されて目立った人物を、匿名アカウントから攻撃して正義を主張する。そこには、相手の気持ちを考えず、「ストレスを発散したい」「攻撃したい」「晒し上げたい」といった思いがあるように見受けられます。
こうして拡散されているのは、“不幸な驚き”ばかりです。私たちは、そんなネガティブな世界を少しでも減らしたい。怒りやいらだちではなく、嬉しさや喜びが広がる世界を目指したい。
2024年12月にリリースした「mixi2」では、投稿への返信欄に「やさしいことばで返信しよう」というメッセージを表示しました。感情を表現するスタンプやエモテキ(投稿の文字や背景色にアニメーションを追加することで感情を表現できる機能)も、幸せな驚きを広げるための仕組みです。

写真提供:MIXI
さらにMIXIでは、私たちの意思決定の軸である“MIXI WAY”として「ユーザーサプライズファースト」を掲げています。
一般的にはよく「ユーザーファースト」という言葉が使われます。これは多くの場合、お客様が課題に感じていることを第一に解決し、お客様が心地良いと感じることを提供しなければならないといった意味に捉えられます。しかし当然ながら、より良いサービスの形は、お客様が完全に知っているわけではありません。
私たちも、過去には「ユーザーファーストだ」として、お客様の意見を集めてはそのまま取り入れようとしていたことがありました。しかしお客様は、私たちのサービスの未来を見据えているわけではありません。むしろ未来のサービスを形づくり提案するのは、私たちプロの仕事です。ユーザーの声だけに頼れば、プロとして責任を果たしていないことになります。
では、人々から本当に喜ばれるには、どうすればいいのか。それが「幸せな驚き」を想像することです。
複数の広告代理店からテレビ広告の見積もりを取った際、A社よりB社の方が高かったとします。でも「B社のほうが絶対に面白い」と感じたならB社を選ぶ。「コストが安いからA社にする」という判断ではなく、「どちらがよりユーザーを驚かせ、楽しませられるか」を基準に意思決定するからです。MIXI WAYは、私たちがそうした意思決定をするための指標です。
幸せな驚きとは、相手の想像の一歩先を行く“伸びしろ”とも言えます。想像以上の伸びしろを提供しているからこそ、お客様に喜ばれている。私たちの売り上げなどの数字は、すべてお客様に提供した幸せな驚きの対価なのです。
世界のMIXIになるまで
MIXIといえばSNS「mixi」を思い浮かべる人が多いですが、いま主にスポーツ、ライフスタイル、デジタルエンターテインメントの3つの領域で事業を展開しています。現在はデジタルエンターテインメントが他の事業を支えていますが、将来的には3事業すべてが自立し支え合う収益構造にしていきます。
いまは特に海外投資比率を高めている段階です。たとえば「モンスト」のインド進出に加え、北米を中心とした海外市場における「みてね」の収益力強化など、新たな成長機会を積極的に追求しています。

グローバルで見ると、コミュニケーション企業と呼ばれるプレイヤーには、Xを運営するエックス・コープ(X Corp.)や、GAFAMの一角であるFacebookを運営するメタ(Meta Platforms)社などが存在します。MIXIが世界で戦うには、こうしたビッグテックから当然のように認知されていく必要があります。
そのためにも、まずは国内での正しい認知を獲得しなければなりません。現在はまだ、実際に展開している事業と、人々に認知されているブランドイメージが合っていない。そこをマッチさせ、SNSだけではなくゲームやスポーツなどにも領域を広げていることを、多くの人々に知ってもらいたい。
ただMIXIはあくまで国内にとどまらず、グローバルコミュニケーションカンパニーを目指しています。最終的には、北米のSNS企業にとって脅威となる影響力を持ち、グローバル市場で存在感を示す企業に成長していきたい。スマホゲームの収益ランキングで世界一を獲得したことのあるモンストをはじめ、MIXIはすでにグローバルで戦えるビジネスを有しています。
「日本からもコミュニケーションを掲げる会社が出てきた。SNSだけではなく、ゲームやスポーツの事業も扱っている。強力なライバルだ」――そう言われる企業にならなければいけません。
そんな将来を描きながら、私たちはどこまでも「幸せな驚き」に包まれた世界を生み出していきたいと思っています。
編集・取材:金藤良秀(クロスメディア・パブリッシング)