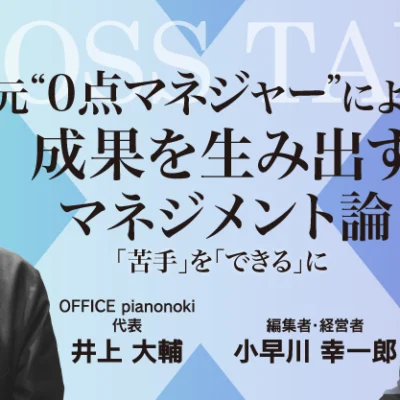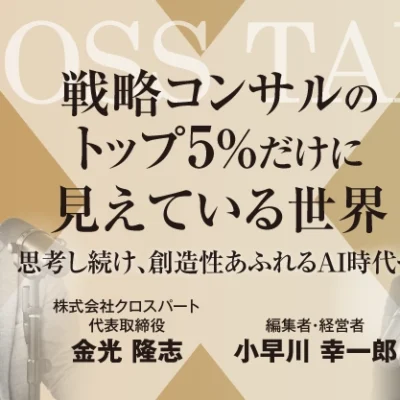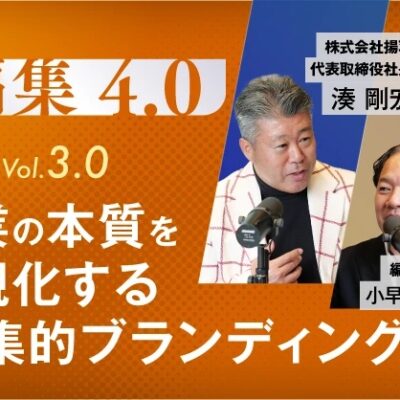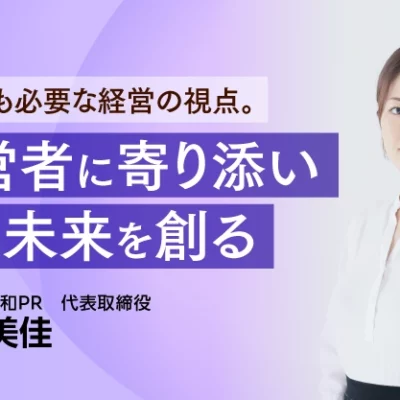PURPOSE
金融資本市場の力で、世界と共に挑戦し、豊かな社会を実現する
金融資本市場をリードする野村ホールディングスは、2025年12月に創立100周年を迎えます。その節目を前にした2024年4月、同社グループは新たなパーパスとして「金融資本市場の力で、世界と共に挑戦し、豊かな社会を実現する」を策定しました。
のべ1万人以上の社員が参加し、約3年がかりで行われたパーパスプロジェクト。パーパスの推進役であるCHRO兼CHOの尾崎由紀子氏は、会社のパーパスを考える前に、まず個人のパーパスを考えることが重要だと語ります。

尾崎由紀子(おざき・ゆきこ)
野村ホールディングス株式会社 執行役員 チーフ・ヒューマン・リソーシズ・オフィサー(CHRO)兼健康経営推進責任者(CHO)。野村證券株式会社 常務 人事担当。
化粧品製造会社SEからキャリアをスタートし、その後、投資銀行部門、人事部門の専門職として外資系証券会社に2社勤務。2008年に野村證券へ入社し、現在は、野村ホールディングスCHROとしてグループ全体の人事戦略、人材開発、DEI及び人事オペレーションを統括。
100年の節目に会社の存在意義を考える

当社は野村證券でよく知られていますが、国内のウェルスマネジメント部門のみならず、グローバルな投資銀行ビジネスであるホールセール部門、アセットマネジメントビジネスを中心としたインベストメント・マネジメント部門や信託銀行、デジタルを活用した金融サービスなど、多岐にわたる事業を展開している総合金融機関です。創立の1年3ヶ月後にはニューヨーク出張所を開設し、早くから海外市場に挑戦してきました。
現在はグループ全体では世界約30の国と地域に約2万7000人、国内には約1万5000人が勤務しています。日本から海外に人材を派遣する企業は珍しくありませんが、当社では、海外で働く人材の半数近くが現地採用の人材です。
私は野村ホールディングスのCHROとして、野村證券を含むすべてのグループ会社の人事を統括し、CHOとして社員の健康やウェルビーイングを推進しています。
野村ホールディングスは、2025年12月に創立100周年を迎えます。社会構造が劇的に変化し世界情勢が急速に変動する中で、私たちの仕事のあり方や存在意義を改めて考える機会につなげたいというグループCEOの強い想いから、2021年に私を含む役員、部長10数人のメンバーでパーパスプロジェクトがスタートしました。
半年以上をかけて、週末に集合し、そもそもパーパスとは何か、どのようにつくっていくべきか、時間をかけて皆で議論しました。
個人パーパスの実現が会社の発展につながる
パーパスが果たす役割を突き詰めていくと、会社のパーパスと同じくらい、個人のパーパスが大切であることが見えてきました。個人のパーパスがある人は、その達成に向け、明確な考えや意志をもって前向きに行動ができます。会社のパーパスと個人のパーパスに重なる部分があれば、会社で働くことが個人のパーパスの実現にもつながり、社員は会社で働く価値を見出すことができます。
会社にとっても、いろいろなパーパスや価値観をもった人が集まることで、組織の多様性が高まります。お互いの想いを理解することで、心理的安全性が保たれた健全な組織運営にもつながる。それは、新たな価値を創造する土壌となり、相乗効果で会社全体のパフォーマンスを上げることに寄与します。
そこで、まずはスターティングメンバーで個人のパーパスを考えました。自分の強みは何か。自分は人生で何がしたいのか。自分は何のために働いているのか。一人ひとりが人生の目的について考える先で、「なぜ自分は野村で働いているのか」という、会社における個人の存在意義が見えてきます。
個人のパーパスを他者と共有し、互いに理解することも重要です。パーパスについて語り合う中で、相手のことを深く知ることができるからです。
個人パーパスを考え、共有する取り組みと並行して、当社グループのパーパスについても議論を進めました。野村ホールディングスは100年後、何を世の中に提供しているのか。私たちが期待する未来の会社はどのような姿をしているのか。さまざまな意見が出され、徹底的に話し合いました。
3年間・1万人で考えた野村グループのパーパス

スターティングメンバーでの検討開始から約半年後、この取り組みをグループ横断の「Nomuraパーパス・ジャーニー」プロジェクトとして拡大しました。部門や国を超えて、国内外の社員1万人以上が対話し、個人のパーパスと当社グループのパーパスについて意見を交わしました。プロジェクトにかけた期間は、約3年におよびます。
なぜこれだけ多くの人を巻き込み、たくさんの時間をかけたのか。それは、パーパスを言語化することだけをゴールとせず、「考える過程」を重視したからです。個人と会社が目指すところについて、一人ひとりが深く思考し、自分なりの言葉にしていく。仕事で直接関わらない同僚や海外のメンバーと対話することで、社内のコミュニケーションも深まりました。
当社グループのパーパスを社員が考えることで、一人ひとりが「自分ごと」として捉えられるという効果もあります。トップダウンで決定事項を一方的に伝えられるより、社員が議論に参加したほうが、パーパスへの共感が高まります。
「Nomuraパーパス・ジャーニー」を通して、会社の存在意義がさまざまな言葉で表現されました。多くの社員から寄せられたキーワードを中心に少しずつ候補を絞っていき、何度も推敲を重ねて、2024年4月に「金融資本市場の力で、世界と共に挑戦し、豊かな社会を実現する」を当社グループのパーパスとして発表しました。
一人ひとりが幸せを感じられる豊かさを
「金融資本市場の力で」は、金融資本市場こそが私たちの強みであるという意思表示です。将来的に金融の枠を超えてビジネスを展開する可能性はありますが、創業以来、当社の軸は金融資本市場にあります。グローバルなネットワークを生かしながら、リスクマネーを循環させ、経済の成長に貢献する。証券、直接金融だけではなく、広く「金融資本市場」を通じて、経済全体の発展に貢献したいという想いがあります。
グローバルファームとして、当社の社員やお客さまは世界中に広がっています。そのすべてのステークホルダーと新たな価値の創造に挑んでいくという決意を「世界と共に挑戦し」に表しました。「挑戦」は、当社の価値観「挑戦・協働・誠実」にもあるとおり、グループに共通するカルチャーでもあります。現状に満足せず、常にチャレンジする。それが金融資本市場のリーディングカンパニーとしての責務だと考えています。
「豊かな社会を実現する」の「豊かな」が意味しているのは、経済的な”豊かさ”だけではありません。人々の幸福感のような精神的な”豊かさ”や安心して暮らせる自然環境の”豊かさ”などを包括した、社会全体の”豊かさ”を表現しています。お金を循環させることで、一人ひとりが幸せを感じられる”豊かさ”の実現を目指すという覚悟を示しています。
パーパス浸透のために全社員でディスカッション

パーパスプロジェクトに参加していない社員もいるため、全社的にパーパスを浸透させる取り組みが重要です。全社員参加の「パーパス・ディスカッション」では、策定した経緯やその意味を伝えたほか、個人のパーパスを考える時間も設けました。個人パーパスは仕事と関連しなくても構いません。まずは個人として大切にしたいことを考え、その後で会社のパーパスとの重なりを考えます。
私自身のパーパスは、「一人でも多くの人を笑顔に」です。仕事やプライベートにおいて、相手に笑顔でいてほしいと考えています。人事の役割として、さまざまな人と接する中で、どんな時でも相手が自分らしく笑顔でいられるようにすることが私の使命だと思っています。
このような考え方を社員に参考にしてもらうために、役員クラスのSMD(シニア・マネージング・ディレクター)が個人パーパスをシェアするビデオメッセージを全社員に発信しています。また、私自身が支店を訪問して社員と直接議論する「パーパス・車座ミーティング」も行っています。これは、パーパスの浸透がどれほど重要かを社員に伝える良い機会となっています。
他にも社内のイントラネットやニュースレターを通じて、パーパスの言葉や想いを伝え続けています。新入社員研修やキャリア採用の懇談会でもパーパスをテーマにした議論を行い、新たに入社する方々にも浸透するよう努めています。
受け継がれてきた創業の精神は変わらない
現在、当社グループのパーパスを知らない社員はほとんどいないと思います。パーパスが浸透し、理解が深まることで、チームや組織に一体感が生まれています。「何のために働いているのか」を考えることが、社員の活力や士気の向上につながっていると感じています。
パーパス浸透の取り組みは今後も続きますが、すでに実践段階に入っています。当社グループのパーパスが各部署のビジネスにどのように関連しているかを常に考えています。部門や社員の業務はさまざまですが、野村グループとしての使命は共通しています。それは、金融資本を通じて豊かな社会を実現することです。
パーパスの策定を通じて、社員は日々の業務の根底にあるこの社会的使命を理解し、認識することができました。また、個人のパーパスを言語化し、考え続ける重要性を繰り返し伝えています。「なぜ野村グループで働いているのか」「今の業務のどこにやりがいを感じているのか」「これからの自分はどうありたいのか」を考え続けてほしいと思います。
個人のパーパスは変わっても問題ありません。社会情勢や自分の置かれる環境によって、視点が変化することもあるでしょう。時代や社会、生活の変化に応じてアップデートする。個人のパーパスは、いつ、どこにいても、一生考え続けるものだと思います。
一方で、当社グループのパーパスを策定したことで、時代が移り変わってもぶれることのない、組織の軸が生まれました。当社には、創業者・野村徳七から受け継がれた、金融を通じて社会やステークホルダーに寄与する精神があります。パーパスの策定は新たな定義ではなく、創業の精神を見つめ直す作業だったのかもしれません。これからの100年、そしてその先の未来に向けて、創業の精神に根付いたこのパーパスを継承し、豊かな社会の実現に取り組んでいきます。