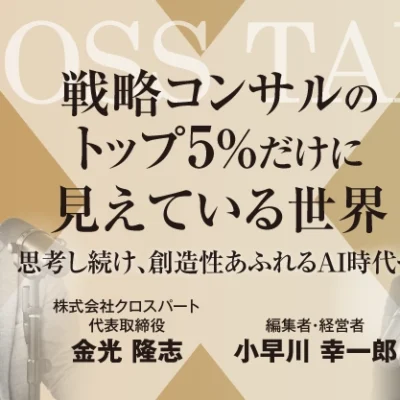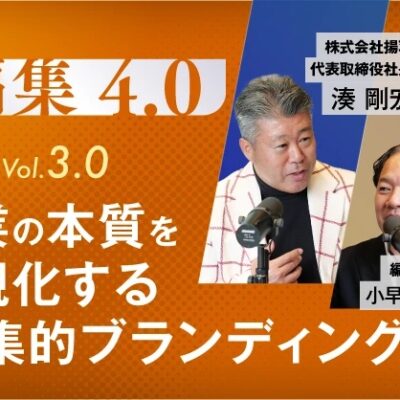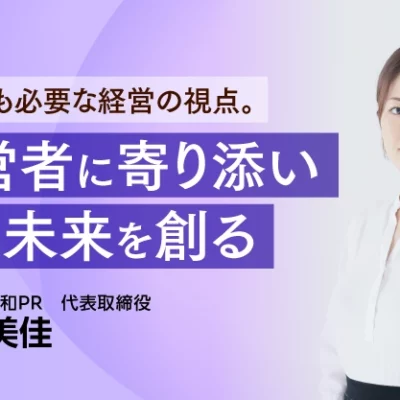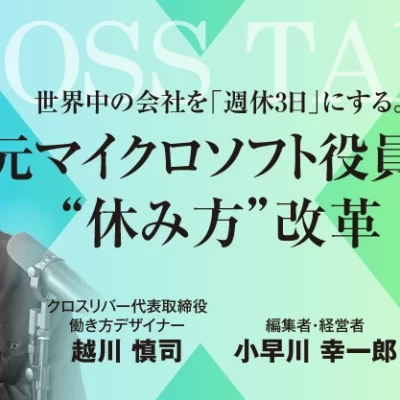PURPOSE
お客さまの『あったらいいな』を超えて、日常の未来を生みだし続ける。
日本の消費者にとって、もはや生活インフラの一部となっているコンビニATM。そのパイオニアともいうべき存在が、セブン銀行です。同社は創業20周年を迎えた2021年4月に、「お客さまの「あったらいいな」を超えて、日常の未来を生みだし続ける。」というパーパスを策定しました。サービスの立ち上げから同社のATMの開発に携わってきた代表の松橋正明氏は、このパーパスをどのように捉えているのでしょうか。日常の未来を生み出すための、同社の新たな挑戦について伺います。

松橋正明(まつはし・まさあき)
株式会社セブン銀行代表取締役社長。釧路工業高等専門学校卒。1998年よりアイワイバンク銀行(現セブン銀行)のATM開発に参画し、2009年同社ATMソリューション部長に就任。11年以降執行役員 を経て、22年6月より現職。一般社団法人金融データ活用推進協会顧問。
テクノロジーの力で生活者の新たな日常を創り出す

当社の事業の中核は、日本全国のセブン-イレブンに設置されているATMプラットフォームです。キャッシュレス化が進む現在では、リアルとバーチャルの貴重な接点として、多くのお客さまにご利用いただいています。もともと当社は、「コンビニでお金を下ろしたい」というお客さまのニーズから生まれた会社です。金融という枠にとらわれず、お客さまが便利だと思うサービスを提供し続ける。そのことは、今も昔も変わらない当社の原点です。
私自身のお話をすると、北海道の釧路高専という学校の機械工学科に通っていました。高専ではいろいろな技術に触れましたが、一番大きかったのは「技術を学ぶ技術」を知ることができた点かもしれません。
製品でもサービスでも、何かが事業として成り立つためには、多様なテクノロジーを有機的に組み合わせることが必要です。そのとき必要なのは、特定の技術に関する専門的な知識だけでなく、複数の技術の原理を組み合わせ、応用することです。
例えばATM事業では、現金を扱うのでハードウェアやセキュリティの技術はもちろん、データを送受信するための通信技術やソフトウェアの技術も必要です。そのように、さまざまな技術を瞬間的に把握して、イノベーションの知の結合を起こす。そのことは、私がキャリアを通じてずっとやってきたことといえると思います。
昨年から始めた、「+Connect(プラスコネクト)」というATMプラットフォーム戦略でも、テクノロジーの融合でお客さまの生活を便利にするサービスを目指しています。これまで窓口や対面でしか行えなかったあらゆる手続き・認証が、セブン-イレブンに行ったらいつでもできるという世界を創ることが、この事業構想の柱になっています。
パーパスが多様な人材の「共通言語」になる

コンビニにATMがあることが当たり前の風景になり、ATMプラットフォーム事業が成熟期に差し掛かった現在を、私は第二創業期と捉えています。創業20周年を迎えた2021年には、「お客さまの「あったらいいな」を超えて、日常の未来を生みだし続ける。」というパーパスが定められました。
「『あったらいいな』を超える」という部分には、お客さまの自覚しているニーズを超えて、潜在的な願いを形にすることで、お客さまの生活をより豊かにしていくという想いを込めています。そして、「生みだし続ける」には、一度叶えて終わりということではなく、その姿勢を貫き通すこと。加えて、いろいろな企業のみなさんとつながりながら事業を拡張していくという意味も含めています。
当社は、中途入社の社員も多く、人材の流動性が高い会社です。そこに、創業当時のことを知らない若手社員もどんどん増えてきます。すべてのメンバーが同じ方向を向いて、高い意識で活躍できるような環境を整えるために、パーパスの策定は非常に有効でした。
具体的なステップとしては、まずは社員だけでなく、社外のステークホルダーや有識者を含めた総勢200名から情報収集を行いました。さらに、経営層と有志メンバーの46名で計14回のワークショップを実施し、これまでどういった理念のもとサービスを作り出してきたのか、今後どういう姿になっていきたいのかを話し合いました。最終的には、これらのワークショップを通じて明文化された存在意義をさらにブラッシュアップし、全社員へのアンケートでパーパスを策定しました。
パーパスの策定によって、改めてわれわれの立ち位置を知り、共通認識を持つことができたのは大きな収穫でした。パーパスに「金融」という言葉を使わないことに決めたのもそのときです。われわれの存在価値は、いままで世の中になかったものを作ることだと考えたとき、金融という枠にとどまらず、広く社会課題を解決していく方向性を再確認しました。パーパスは、それを体現したメッセージになったと思っています。
パーパスの浸透が「日常の未来」の実装につながる

パーパス策定の過程で印象的だったのは、社員のパッションが可視化されたことです。「どういう未来にしたいか」というテーマで話し合ったときは、「こんなに熱い想いを持っているんだ」と驚くこともありました。もともと社内カルチャーとして年齢や役職に関わらず発言しやすく、チャレンジを歓迎する環境ではあるのですが、それがより解放されたように感じます。
パーパスは、すべての社員に浸透することで、より効果が上がります。策定した当初は、自分事化できない社員もいたと思います。特にバックオフィスや管理部門の方にとっては、自分たちが日々行っている業務がどうパーパスと結びついているか、想像するのが難しい側面もあったかもしれません。
そこでパーパスの策定からこれまでに、さまざまな部署の社員と経営層が直接対話するタウンミーティングを70回以上開催しました。社員一人ひとりの業務がどうパーパスに結びついているかを実例を交えて話すことができましたし、私自身、現場でいま何が起こっているかを把握する良い機会になりました。
そうして社内にパーパスが徐々に浸透し、社員の意識も変わり始めました。パーパスを起点にしてアイディアを出したり、ロジックを組んだりすることが増えてきました。銀行や役所での手続きを、ATMで行えるようにすることを目指した「+Connect(プラスコネクト)」も、お客さまの期待を良い意味で裏切り、日常の未来につながるようなサービスとは何か、と考えた結果生まれたものです。
ありがたいことに社外にもパーパスが定着し始めました。ある時、パートナー企業との打ち合わせで「A案とBの案があるのですが、セブン銀行さんのパーパスに照らすとB案だと思います」と担当者の方が言ってくださいました。
こちらからパーパスを押し付けるのではなく、協力していただいている企業の方までもがパーパスを理解したうえで、ご提案していただけています。パートナーとの信頼と共感というのは、当社がずっと大事にしているDNAの一つでもあり、非常にうれしかったですね。
そのほかには、パーパスアワードというものを毎年実施していて、今年で3回目になります。パーパスの実現に貢献した取り組みをグループ全体で共有し、社外取締役による最終審査を経て、表彰しています。
例えば、ATMの効果音が「お金ないでしょ♪」に聞こえるというSNSの投稿を受けて、第4世代の新型ATMを実装する際に、取引音を変更するプロジェクトがありました。この対応は、国内の大手メディアでも取り上げていただくなど、大きな反響を呼びました。このように、お客さまの想像を超えてサービスを改善する取り組みが、毎年どんどん出てきています。
パーパス策定の背景にある、挑戦を歓迎するカルチャー

お話したような取り組みが生まれた背景には、当社のカルチャーがあります。新しいチャレンジを奨励し、仮に失敗してもそれをまた糧にする。
私自身も社会人になって間もないころ、大きな失敗したことがありました。ある製品を作る過程で、大きなコスト削減につながる処理があったのですが、実装するためには数千万単位の投資が必要でした。これはまったく新しい素材を使った画期的な手法だったのですが、いざ量産する段階になって、一定の確率でエラーを起こすことがわかり、結局廃棄することになってしまいました。
しかし、新しいアプローチの重要性は周りも理解してくれていて、誰からも責められることなくチャレンジし続けることができました。もしあの時、失敗を理由に仕事を外されていたら、いまの私はなかったかもしれません。
当社では、チャレンジ大歓迎です。「手挙げ制度」が浸透しており、社歴が浅い社員でも、新しい企画を立ち上げる機会が与えられています。中途入社の社員が全体の8割を占めていますが、そのような制度を活用することで、組織の硬直化を避けることができています。
やりたいこと(ウィッシュ)があれば、そのテーマに関して組織の枠を超えて活動し、日々変化するお客さまのニーズに柔軟に対応できます。多様なバックグラウンドを持つ社員が集まっていることは、組織の一体感を損なうと考える人もいるかもしれませんが、当社ではパーパスを実現するうえでプラスに働いていると思います。
新しいことに挑戦する際、大事なのは「何をやるか(What)」ではなく、「なぜやるか(Why)」だと思っています。WhatやHowは時代によって変わりますが、Whyは変わらない。例えば、「新しいツールを使おう」「この媒体で広告を打とう」というところが起点になってしまうと、肝心の「なぜやるか」が置き去りになってしまいがちです。そうではなくて、顧客体験向上のために何ができるか、どんな「あったらいいな」が考えられるか、という方向でアイディアを出してみる。そのように機能する狙いでパーパスを設計しました。
「なぜやるか」を掘り下げていったときに、われわれがやるべきなのは、変化をつかむことだと思っています。お客さまが日常生活において何を好んでいるか、どういう傾向を持っているかということを、事業者として知る必要があります。
セブン-イレブンのDNAとして、「徹底的にお客さまの立場で考える」というものがあります。当社のATMプラットフォーム事業にも、それが受け継がれています。
私は実店舗でのお客さまの様子を観察することもあります。いわゆるデザイン思考です。例えば、若いお客さまの中には、お財布を持たずに来店される方もいます。一方で、こういう時には現金を使う、と決めている方もいる。現金の扱い方だけを見ても、十人十色です。あるいは、女性のバッグの大きさなども、時代によって変わってきています。やはり昔のように大きな財布を持っている方は減っているのか、といったことも考えます。
最近はイートインスペースがあるので楽になりましたが、昔だったら怪しく思われているかもしれません。
「誰一人取り残されないデジタル社会」実現のために

お客さまの生活をより快適に、より便利にしていく。そのためには、新しいことにチャレンジしつつも、守るべきところは守らなければなりません。特に当社の場合、お金や個人情報といったセンシティブなものを直接的に扱いますから、セキュリティ面は万全でなくてはなりません。攻めの業務と守りの業務、そのバランスは常に意識しています。
先ほどチャレンジを歓迎する社風と言いましたが、それは守りの業務を軽視しているわけでは決してありません。さまざまな法制度への対応や、セキュリティ基準の変更、また社員のエンゲージメント施策など、社会的にスポットライトを浴びるような業務ではなくても、われわれの会社にとってなくてはならない仕事はたくさんあります。
今回策定したパーパスは、そのような当社の業務にすべてに関わるものです。新たなATM戦略の「+Connect(プラスコネクト)」も、実現のためには全社的な取り組みが必要だと思っています。社会的な潮流やお客さまのニーズの変化に対応し、「あったらいいな」を超えるサービスを提供し続けるためには、すべての社員がパーパスの下で自分なりのチャレンジを続けることが不可欠です。
金融業界の常識にとらわれていたら、そもそも当社のサービスは生まれていません。いままでの「当たり前」を疑い、新しい「当たり前」を創る。これからも、テクノロジーと人の力で金融業界の常識を覆し、すべてのお客さまに新しい価値を届け続けたいと思います。