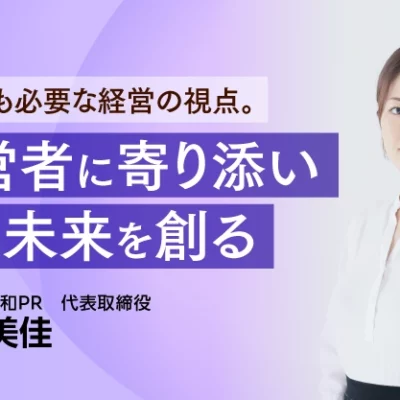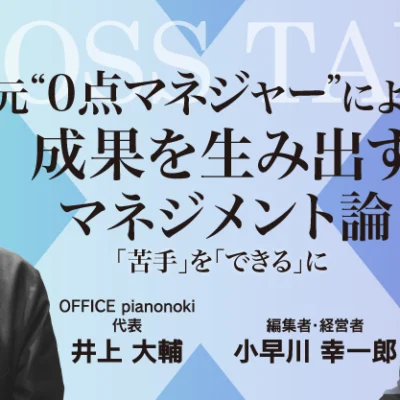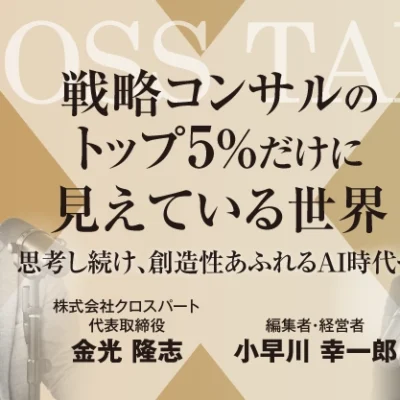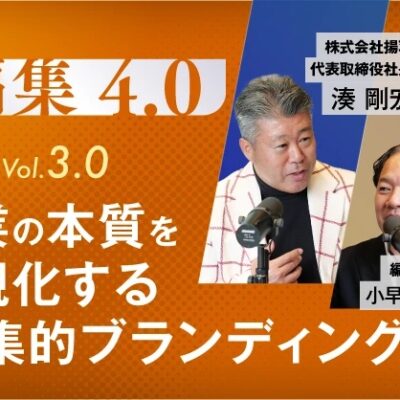社員自身が自分のスキルを管理するシステムを独自に開発した、スキルティ株式会社。人材不足に悩むIT業界を中心に導入された「スキルマネジメントシステム」の「skillty」(スキルティ)は、さまざまな業界から注目されています。「社会人基礎力」に重きを置いた、人に依存しない教育システム。社員の成長意欲を高め、企業全体の成長を最大化する教育には何が必要なのでしょうか。

中塚敏明(なかつか・としあき)
スキルティ株式会社代表取締役社長。1976年生まれ。1998年武蔵工業大学(現・東京都市大学)電気電子工学科卒業後、同大学院へ進学。卒業後、東日本電信電話株式会社(NTT東日本)入社。法人営業本部にて、超大手企業のさまざまなネットワークインテグレーションを手がける。2011年「ビジョナリーカンパニーを作りたい」との思いのもと、ネットビジョンシステムズ株式会社を設立。2016年「世の中の『繋がる』を支えるため、ITインフラエンジニアを輩出し続ける」というビジョンを掲げ、ネットワークエンジニアの養成スクールを開校。若い世代のエンジニア育成に取り組む中で、成長環境を整えれば組織力が高まるだけでなく、従業員エンゲージメントが劇的に向上することに気づき、能力開発をマネジメントするスキルマネジメントシステム「skillty」を考案・開発。リンクアンドモチベーション社の従業員エンゲージメント診断・サーベイクラウド国内市場No.1のモチベーションクラウドにて、従業員エンゲージメント上位2%となる組織偏差値70を超え、同業種同規模ランキングNo.1の称号を得る。2022年スキルティ株式会社を設立、代表取締役社長に就任。中小・ベンチャー企業の従業員エンゲージメントと人材育成を底上げするために、スキルマネジメントの普及に注力
自ら進んで成長できる環境をつくる

教育において、大事な要素は何か? それは「成長意欲」です。本人の成長意欲を促すために、人による教育やシステムによる教育があると考えています。
弊社が開発した「skillty」によるスキルマネジメントの強みは、社員の成長を促す「エンジン」になることにあります。「skillty」を通して行う教育とは、単純に、仕事に必要な知識を身につけるというものではありません。システムによって、社員が自ら「気づきのセンサー」を実装していくようなイメージです。
例えば、パイロットの仕事を想像してみてください。実際に飛行機に乗って飛ぶ前に、必ずいろいろチェックしますよね。同じように、業務に取りかかる前や業務を遂行していく中で、「skillty」を確認することによって「気づき」を得られます。「手順を間違ってないか」「漏れているものはないか」と、自らアラートをかけて、精緻に仕事を行うことができるようになるのです。
機能の一例として、スキルを因数分解し、成果に結びつける「アクションリスト」は、「どう動けばいいか」「どう力を発揮したらいいか」が、一目でわかるようになっています。スキルの習得や向上のためにやるべきことが具体的になっているので、実際に仕事を行うイメージが見えてくるのです。
「skillty」を通して、スキルを可視化し、スキルの向上を習慣化させることで、社員の成長意欲は高まります。さまざまなスキルを可視化した「スキルマップ」がチェックリストに反映され、社員が定期的にセルフチェックを行うことで、成長のためのPDCAサイクルを強化して、スキルの習得度を高め、個人の成果を促進させます。 このように、「skillty」の導入によって、社員が自ら成長できる「環境」を構築することができるのです。
中小企業の社員教育を変えたい

私は新卒でNTTに入社し、ネットワークエンジニアとして働いた後、未経験者からITエンジニア、特にネットワークエンジニアの人材を育てていこうと、いまの会社を立ち上げました。ただ、専門的なスキルをメインにした教育に力を入れていましたが、離職率は40%と高く、マネジャーからは「せっかく教えてもやめてしまう。教え損だ」という声が挙がっていました。
そこで、会社の方向性や評価制度を整えつつ、マネジャー陣に部下の教育に力を入れるよう指導しました。その結果、部下のエンゲージメントは高まったのですが、今度は、部下への寄り添い疲れで、マネジャー陣がやめてしまうということが起こりました。
「本当に社員教育を人にずっとやらせていいのか」――そんな疑問が生まれました。教えられる側からも、「人によって教え方が違う」「あの人はいいけど、この人は駄目だ」などの声が聞こえてきました。
教育を人に頼り過ぎると、部下かマネジャー、どちらかに不満が偏る「ゼロサムゲーム」になってしまう。人ありきの思考ではなく、「仕組み思考」にしていかなければならないと気づきました。
どうしたら、社員がマネジャーに依存せず、自主的に成長できるか。考えた結果、教育システムをつくることにしました。
第一段階として、スキルをエクセルで可視化し、新人を対象に実施したところ効果がありました。マネジャーからも「指摘がしやすい。教えやすい」と好評でした。その後、社員全体の育成も含めたシステムに整えて使用したところ、管理職の負担が減り、マネジメントもかなり楽になったのです。社員のエンゲージメントが大きく回復し、離職率も減少しました。
経営者のなかには、「教育システムなどつくらず、スキルの高い人物を採用すればいいじゃないか」と思う方もいるかもしれません。私がNTTに入社した当時も、仕事について教えてくれる人があまりおらず、各自が自分で覚えていくという雰囲気でした。少し前はそういうところが多かったと思います。いまでも、会社が一番ほしい人材は自分から進んで学んでいける人でしょう。
しかし、採用の過程で、そこを見極めるのは難しい。そして、大企業と違い、中小企業はそういう人材をなかなか採りにいけません。やっと見つけてアプローチしても断られるパターンが多い。だからこそ、中小企業において、システムによる社内教育は必要なのです。
社会人基礎力を求める声に答える

いま私たちは、スキルマネジメントの中でも、特に「社会人基礎力」のようなノンテクニカルスキルのマネジメントに力を入れています。
社会人基礎力は、2006年に経済産業省が提唱した「職場や地域社会で多様な人々と仕事をしていくために必要な基礎的な力」のことです。「前に踏み出す力」「考え抜く力」「チームで働く力」という3つの能力(12の能力要素)から構成されています。
スキルの習得というと、専門スキルつまりテクニカルスキルを高めようとしがちです。私自身、スキルマネジメントにたどり着くまでは、「専門スキルをいかに身につけさせるか」が重要だと思っていました。しかし、社会人基礎力がないまま、専門スキルを詰め込もうとしても、なかなか身につかないのです。
社会人基礎力とは、「OS」のようなものです。パソコンを使うときには「OS」を入れてから、「アプリ」をダウンロードしますよね。同じように、社会人基礎力がしっかり身についたうえで、専門的なスキルが身につき、成果につながっていきます。主体性や前に踏み出す力、考える力、特にチームで働く力などを育むことで、エンゲージメントにもつながります。
ただ、ノンテクニカルスキルのマスターは、教える側・教えられる側どちらにとっても、想像以上に難しいものです。学校で教えませんし、効率的よく教える仕組みもありませんから。例えば、人との関わり方や、人と連携して仕事の成果を出すための具体的なアクションというものは、簡単に教えられるものではありませんよね。
さらに、ノンテクニカルスキルは徹底して教育していかないと身につかないものなのです。研修後も現場の社員を追って、学びが生かされているか検証するということは物理的に不可能でしょう。そもそも、全新入社員に対して一斉に研修を行うようなやり方はお金も時間もかかるうえに、効果は持続しません。
「skillty」では、日常業務の中でそれらの習得度を、社員自らチェックすることが可能で、具体的なアクションも可視化して提示しています。おかげさまで、企業として数値的な目標を達成し、事業の集大成のひとつとして本を出版した後は、経営者の方々から「成長環境って、本当に大切なんだね」「うちも成長環境と評価制度を整えないといけないよね」とお声がけいただくようになりました。高いスキルが必要とされる分野でも、専門スキルは抜群なのに、社会人基礎力は二流三流……という社員が多く、現場は大変苦労しているという話を聞きます。
最近はIT以外の業界から問い合わせが増えています。官公庁や飲食チェーン、美容系など。病院でもトライアルが始まっています。製造系の会社では、社会人基礎力を盛り込んだ評価制度を制作し、実践するためのコンサルも行っています。地方の経済誌からも、スキルマネジメントや社会人基礎力をテーマにした連載の執筆を頼まれています。どの業界の経営者の方も、社会人基礎力を育てる必要性とそれを教える難しさを感じているように思います。
コロナ禍もあり、社会全体を通して、一歩踏み出す力やチームで働く力などが失われている中、「skillty」が貢献できる部分はまだまだたくさんあると感じています。
AIマネジメントの時代に向かって進化を続ける

「skillty」は、現場の問題に取り組む中で生まれました。プロジェクトを立ち上げ、私がディレクターのような立場でメンバーに指示を出し、2年ほどかけて完成させました。
現在のバージョンでは、どの会社でも使えるよう、汎用性のあるものを1から作成しました。社会人基礎力の習得度を示すレーダーチャートをより詳細に分析できるようにするなど、お客様の声を反映し、バージョンアップを続けています。
いまはChatGPTを取り入れた試作品の制作も進めています。AIによって、マネジメントも評価も自動化しようと考えています。AIによる評価には抵抗がある人もいるかもしれませんが、同じように、人が人を評価することに対して疑問を抱いている人もいると思います。
公平性をどう担保するかは慎重に検討する必要があると思いますが、第三者として、会社の人事にAI評価を取り入れるのはありなのではないでしょうか。「ここが足りてないですね」など、人から指摘されることを、AIに指摘されたほうが、揉め事を避けられる可能性もあります。
さらに、部下に対して指導する時間を捻出する手間も省けます。評価がワンボタンでできたらどうでしょう。画面上で「厳しめ上司」のボタンを押すと厳しいコメントが出て、「ほめ上司」のボタンを押すと相手を持ち上げる文章ができて、フィードバックする。いま、そのような機能を加え始めています。
「AI上司」や「AIマネジメント」の時代がきているのを感じます。スキルマネジメントにおけるAI活用の需要は今後も高まっていくでしょう。
システムが人による教育をカバーする

ある福祉幸福に関する調査によると、人が一番不幸なのは上司と過ごす時間だそうです。そうなると、1on1などは相当苦痛でしょう。本当に尊敬する上司って、そういないものですよね。そもそも、社内で相性が完璧な人材の組み合わせを見つけるのは難しいものです。
1on1を現場の人間に任せると、たいていネガティブな情報が回ってきます。中身のない雑談になってしまって、部下が「何の時間だったんだ」「嫌な上司となんで雑談しないといけないんだ」と困惑するのです。1on1は、部下が求めるタイミングで、求めるものを与えられないと機能しません。つまり、仕組み化しないと失敗します。また、個人の力量にも依存します。
弊社では、基本的に「skillty」を使用して1on1を行います。会話の内容は、「skillty」が提供します。システムを見ながら、部下の「どこが弱いのか」「何が足りてないのか」「何に困っているか」などを、1対1で、一緒に見ていくのです。個人のコーチング力やティーチング力の不足をシステムがまかなう。こうしたところも、システムが入ることでうまく回っていきます。
とはいえ、人による教育も必要です。部下の話を聞いて、「それって、こうなんじゃない?」と、本人が気づけなかったことに気づかせる。相性もあると思いますが、人によるコーチングやティーチングのようなものは必要だと思います。経営者としても、アイデアが固まらないときに、気の合うコンサルタントと話して意見をもらうと考えがまとまりますから。
今後はそうしたこともChatGPTで行うようになるかもしれませんが、「感情を受け止める」というのは、やはり人でないとできません。対面でないと、部下からのSOSなどもつかめませんから、1on1のようなことは必要でしょう。先ほどのAIによる評価でも、「いまは落ち込んでいるから、ポジティブなコメントをしよう」といった人による判断は必要です。「察知する力」は人間ならではのものだと思います。
「skillty」を通して、AIによるスキルマネジメントを進めながら、人材教育のありかたを劇的に変えたいと思っています。

従業員エンゲージメントを仕組み化する スキルマネジメント
著者:中塚敏明
定価:1958円(本体1780+税10%)
発行日:2023年2月1日
ISBN:9784295407942
ページ数:232
ページサイズ:188×130(mm)
発行:クロスメディア・パブリッシング
発売:インプレス
Amazon