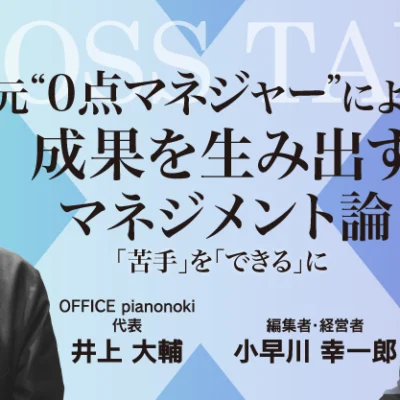「さんまのスーパーからくりTV」や「中居正広の金曜日のスマイルたちへ」など、数々のヒット番組を手掛けた角田陽一郎さん。「コンテンツとは、フレームを満たすためのものではない」と語ります。知的好奇心というアイデアの種がコンテンツとなり、マルチユースされることで、渦を生み出す。
前編では、角田さんが「編集」という仕事に何を求めているのかを中心に、クロスメディアグループ代表・小早川幸一郎がインタビューします。
※この記事はクロスメディアグループが2024年8月に主催したイベント『本とテレビを編集する』の内容をもとに、編集を加えたものです。
>【後編の記事はこちら】知的好奇心というアイデアの種が「渦」を生み出す
「編集」の役割は、書籍や動画を作ることにとどまらず、「人と企業の編集」「事業の編集」「社会の編集」へと広がっていく。本シリーズでは、編集者でありクロスメディア・パブリッシングの代表でもある小早川幸一郎が提唱する「編集4.0」をテーマに、編集の持つ価値をゲストとともに拡大していきます。
編集4.0とは・・・・
編集1.0:メディアの編集
編集2.0:人の編集
編集3.0:事業と企業の編集
編集4.0:社会の編集
※編集4.0の定義はこちら>『【編集4.0:Vol.0.0】編集とは、すでにあるものを組み合わせて新しい価値を生み出すこと』

角田陽一郎(かくた・よういちろう)
1994年 に東京放送(TBSテレビ)に入社。「さんまのスーパーからくりTV」 「中居正広の金曜日のスマイルたちへ」「EXILE魂」「オトナの!」など、数多くのバラエティ番組を担当。2016年12月にTBS退社。現在は、テレビ番組のほか、youtube動画、メディアブランディングなど、さまざまな革新的アイデアを基にビジネスを創造し続けている。 2019年4月からは東京大学大学院人文社会系研究科文化資源学研究専攻文化経営学修士課程の学業にも打ち込む。

小早川幸一郎(こばやかわ・こういちろう)
クロスメディアグループ(株)代表取締役。
出版社でのビジネス書編集者を経て、2005年に(株)クロスメディア・パブリッシングを設立。以後、編集力を武器に「メディアを通じて人と企業の成長に寄与する」というビジョンのもと、クロスメディアグループ(株)を設立。出版事業、マーケティング支援事業、アクティブヘルス事業を展開中。
テレビ制作で培ったスキルを多分野に生かす

小早川 角田さんと初めてお会いしたのは、東日本大震災の直後ですね。
角田 そうですね。僕がテレビの枠を飛び越えようと思ったきっかけは、東日本大震災なんです。それまでは、テレビ番組を作ることをただ楽しむだけでした。震災が起こって「こんなことをしている場合ではない」と思いましたが、僕がボランティアをしても、被災地への影響はたかが知れています。
そんなときに、テレビ番組制作の中で身につけた「フリとオチ」のスキルを生かして、何かできるのではないかと思いました。このスキルはお笑いだけでなく、人を感動させるときなど、あらゆる場面で生かすことができます。まずは本を書くことから始めようと考えていたとき、知り合いを通じて小早川さんに出会いました。
小早川 当時角田さんはTBSに勤めていらっしゃって、会社員ながら本当に自由に仕事をされていましたね。
角田 はい。好き勝手に仕事をしていました。例えば、『オトナの!』という番組は、TBSから予算を貰わずに作っていました。テレビは視聴率から利潤が生まれて、制作費になります。スポンサーからお金を貰えば、視聴率を取らないといけません。「自分はプロデューサーだ」と格好をつけていても、結局は予算管理者でしかないんです。
でも、そのお金を自分で用意できれば、視聴率を取らなくても成立します。自分たちでスポンサーを探して、僕自身が尊敬できる人や、かっこいい大人しか出演しない番組を5年ほどやっていました。
小早川 その前には、デジタルの新規事業を手掛けられていました。
角田 GOOMOというネット動画配信会社を立ち上げ、いまでいう「AbemaTV」のような番組を作りました。視聴者は、番組を見たらポイントが溜まって、それを自分が見たいと思う新番組に投資できます。見たいと思って投資した人がいるわけですから、確実に視聴率を取ることができます。
小早川 さらに、映画監督もされていましたよね。
角田 はい。TBSは毎年沖縄国際映画祭に映画を出品しており、2013年に公開された『げんげ』という映画の監督をしました。
まず、僕はスタッフに「今年の休みは実家に帰っていいよ。映画の種になるようなものを持って帰ってきて」と声をかけました。それが実際に映画として形になったら、実家への旅費などをすべて僕が持つという条件です。
すると、富山県魚津市出身だったAP(アシスタントプロデューサー)さんが、「魚津の名産である“げんげ”という魚を知っているか」と聞いてきたんです。幻の魚と書いて「幻魚(げんげ)」と読みますが、もともと「下の下(げのげ)」と言われ、捨てられていた魚だったそうです。下の下から幻の魚になったエピソードが面白く、そこから映画の脚本をつくり始めました。
やるからには、観客動員数で1位を取りたい。そこでまずは沖縄出身の山田優さんをヒロインにキャスティングしました。そうすれば、沖縄の人が映画を見にきてくれますよね。
次は主人公を誰にするか、です。沖縄国際映画祭は吉本興業が運営しており、映画祭に出品される他の作品では、出演する芸人さんはみんな吉本興業の方でした。ほかの事務所の芸人さんを主人公にすれば話題になると思い、人力舎のドランクドラゴン塚地武雅さんにお願いしました。
制作費がたくさんあるわけではなかったので、魚津市の商工会議所に、撮影にかかる食費、移動費、宿泊費を持っていただけないかと交渉しました。その代わりに魚津で映画撮るという条件にすると、快く承諾してくださいました。クライマックスのシーンでエキストラが3000人ほど必要でしたが、そこも魚津市の協力で無事撮り終えることができました。
沖縄の映画祭に出す作品だから、沖縄出身の俳優さんを使えばお客さんが増えるのではないか。魚津で撮影すれば商工会議所に協力してもらえるのではないか。映画やテレビ番組を作る時には、お金の集め方や人との関係性から編集しています。
想定もしていない「オチ」が生まれる瞬間

小早川 会社勤めをしながら自由に活動されていましたが、独立してからもすごく楽しそうですよね。企業のコンサルタント、大学教授、さらにいまは大学院の学生としても学んでいらっしゃいます。なぜそんなにもいろいろなご活動をされているんですか?
角田 結局、知的好奇心を満たすことが一番楽しいと気付いたんです。
『げんげ』は、映画監督を任されてから公開まで4カ月ほどしかありませんでした。誰かのつくった脚本だと権利関係の手続きに時間がかかるので、オリジナル脚本を書いたんです。僕みたいに映画を作ったことないサラリーマンが、急に魚津を舞台にした映画の監督を任される話です。
プロットを作ってから、撮影の数週間前にロケハンをしました。すると、魚津に寂れた雰囲気の、映画のイメージにピッタリの漁港があったんです。ここなら絶対に良い画が撮れると思い、まずはそこを撮影場所に決めました。
次は、そことは別の場所で、主人公が勤める会社として使う建物を探そうとしていました。でもあまりにも魚津の漁港が良かったので、その1階を漁港組合、2階を主人公の働く会社にすることにしてしまいました。そうすると、撮影中の移動時間が節約できて、スケジュールに余裕が出ます。
そうして撮影をすべて終えて編集に入り、撮影した素材を脚本にそのままはめ込んでいました。すると、漁港の2階に会社があるという設定から「なぜ主人公が魚津で映画を撮影しなければいけなかったのか」という理由がおのずと出来上がってしまった。「漁港の2階に支社があることに、実は意味があった」という一つのストーリーの核になったんです。
何も考えないでフリをしていたら、まったく想定していないオチができてしまった。たまらない興奮を感じました。こうした経験をもっとしていきたいと考えて、いろいろな活動をしています。
人が映像に「リアルさ」を感じる条件とは

小早川 今日のトークテーマは、「本とテレビを編集する」です。角田さんはたくさん本を書かれていますし、テレビだけではなくいろいろなものを編集しています。それぞれに共通することはあります?
角田 例えば、『さんまのスーパーからくりTV』には『からくりビデオレター』というコーナーがありました。田舎のおじいちゃんおばあちゃんが子どもにビデオメッセージを送るという内容です。
この番組で一番大事なのはリアルさです。ではどうすればリアルになるのかと考えたとき、皆さんは3分話したものをそのまま3分の尺で出すことがリアルだと思うかもしれません。でも、実は逆です。編集で映像をカットすると、カット点が見える。そのほうがリアルに見えるんです。
YouTubeは、多くの場合ずっと1つのカメラで撮っていますよね。それで「こんにちは」と挨拶をしてから「あのー」と言うまでの間をカットするというように、必要な部分だけを繋いでいくと、カット点が見えます。若者がYouTubeを好きなのは、カット点があることにリアリティを感じるからだと考えています。
一方で、ドラマは複数のカメラを用意します。3つも4つもカメラを使ってカットを変えることで、シームレスにする。作る側はリアリティを出そうと編集しているのにも関わらず、逆転現象が起こっているんです。
だから僕は映画を作るときも、リアリティを出すためにわざとたくさん編集を加えます。例えば、3分話した内容の大事なところだけを残して1分半にする。時間は半分になっているのに、中身は濃くなって、リアリティを感じることができます。
以前、ある有名なミュージシャンの方から僕が編集したテレビの放送を見て、わざわざお礼の連絡をしてくれたことがありました。「テレビに出ると、編集されて自分の言いたいことがうまく伝わらなかったり、発言を曲解して編集されたりしてしまうのではないかと危惧していた。でも、角田さんの番組だと、喋った時間が半分の尺になっているのに、自分が言いたいことがより伝わっている」と驚かれました。僕はまさにそれが編集だと思っています。
編集される側になってわかったこと

小早川 角田さんはプロデューサーで、人や物を編集する立場でいらっしゃると同時に、コンテンツホルダーとして自分が編集される立場でもあります。両方の立場で違いはありますか?
角田 自分はずっと編集をする側でしたが、自分が編集される側になってから、相手の気持ちがわかるようになり、編集をするのがうまくなりました。
例えば、皆さんもそうだと思いますが、「タレントさんは雲の上の存在である。僕らが傷つくようなことをタレントさんにしても、傷つかない」と考えているところがあるのではないでしょうか。
でも、もちろんそんなことはないんですね。以前、僕がスタッフとして関わるテレビ番組の収録で、面識のあった男性アイドルが髪を切った直後に現場に来たことがありました。僕は彼が髪を切ったことには気づきましたが、特に何も言わなかった。すると収録が終わってから、「角田さん、俺の髪型が変わったことに何も言ってくれないね」と少し怒っているんです。
それ以来、どんなタレントさんや有名人でも、常に「可愛い」「かっこいい」と言うようにしています。言ったほうが喜んでもらえる。そんなことも、自分が編集される側にならないとわからなかったです。
小早川 なるほど。雲の上存在だから気を遣うということではなく、神様に対してわざわざ言わなくてもいいと思ってしまうんですね。
角田 そうです。みんなにいつもちやほやされているのに、スタッフからも同じようにされたら嫌がるのではないかとずっと思っていたんです。
自分が演者になって初めてわかったのは、プロデューサーやディレクターは演者の敵であり、試験官でもあるということ。自分のパフォーマンスがOKかどうかを判断する存在なんです。
演者の側で初めてテレビ番組に出演したときには、一人で戦場にいるようでした。でも、メイクさんだけは味方なんですよ。スタッフとして番組を作っているときは、スケジュールが遅れないように早く終わらせてほしいとメイクさんに頼んでも、融通が利かないこともありました。でも、自分が出演する側になると、メイクさんほど心強い人はいません。「ここのシミ隠してくれます?」や「髪型かっこよくしてくれます?」とお願いすれば、メイクさんだけは味方になってくれます。
ディレクターやプロデューサーをしていたときは、演者さんはスタジオで「今日どんな話をするか」ということばかり考えているのかと思っていましたが、自分が演者になったとき、スタジオで気にしていたのはネッカチーフの角度だった。演者の気持ちがわかることで、編集と演出のやり方も変わってきます。両方の立場を経験したことが、僕にとっての成長につながっていると思います。
>【後編の記事はこちら】知的好奇心というアイデアの種が「渦」を生み出す

教養としての教養
著者:角田陽一郎
定価:1848円(1680円+税10%)
発行日:2023年5月21日
ISBN:9784295408338
ページ数:304ページ
サイズ:188×130(mm)
発行:クロスメディア・パブリッシング
発売:インプレス
Amazon