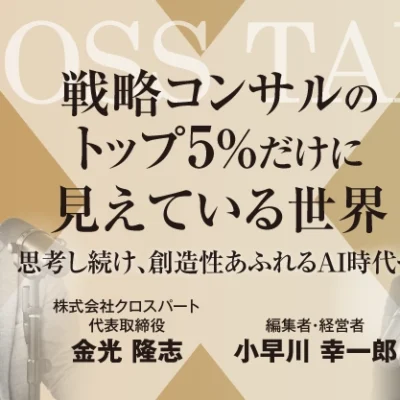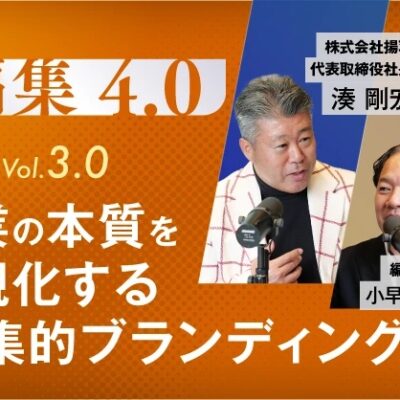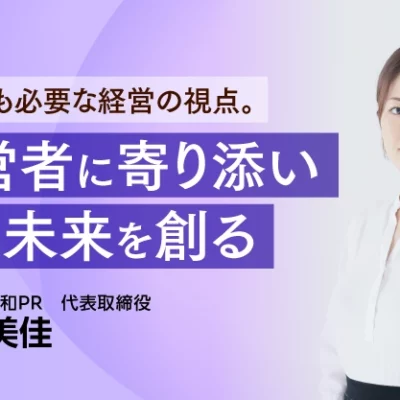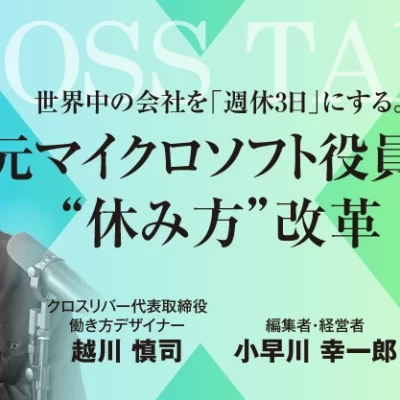2023年4月、ビジネス書としては少し変わった趣の、『魚ビジネス』という書籍が出版されました。魚食文化や漁業について、また魚を美味しく食べる方法など、幅広く教養を得ることができます。著者は「おさかなコーディネータ」という唯一無二の職業を名乗る、ながさき一生さん。一風変わったこの仕事に、なぜ就くことになったのでしょうか。

ながさき一生(ながさき・いっき)
おさかなコーディネータ、株式会社さかなプロダクション代表取締役 、一般社団法人さかなの会理事長・代表、東京海洋大学非常勤講師。
1984年、漁村の漁師の家庭で生まれ、家業を手伝いながら育つ。東京海洋大学を卒業後、築地市場の卸売企業に就職し、水産物流通の現場に携わる。その後、東京海洋大学大学院で魚のブランドや知的財産の研究を行い、修士課程を修了。
2006年からは、ゆるい魚好きの集まり「さかなの会」を主宰し、メディアにも多数取り上げられる。2017年に「さかなプロダクション」を創業し、独立。食としての魚をわかりやすく解説する中で、ふるさと納税のコンテンツ監修や、ドラマ「ファーストペンギン!」の漁業監修を手がける。著書に『魚ビジネス 食べるのが好きな人から専門家まで楽しく読める魚の教養』(クロスメディア・パブリッシング)がある。
「さかなの会」が生まれるまで
将来の仕事のイメージについて、子どもの頃はいろいろなことを考えていましたが、クリエイティブな仕事が多かったように思います。
保育園の頃は祖父の影響でプロレスラーに憧れていましたが、小学校に上がってからは漫画家になりたいと思っていました。これはどちらかというと絵を書きたいというよりも、物語をつくりたいという気持ちのほうが強かったです。
ほかには、昔からゲームや音楽も好きでした。特にゲームのサントラが好きで、中学から高校の前半までは、ずっとゲームの作曲家になりたいと思っていました。
高校は音楽科のある学校へ進学したくて、自分なりにその準備をしていました。ただ、それなりに勉強ができたこともあり、親には反対されました。高校に入ってからも最初は音大への進学が頭の隅にありましたが、学費が高額なこともあり、音大進学は諦めました。
高校では当初文系だったのですが、途中で数学の勉強のコツがわかり、良い成績を取ることができるようになりました。そこで理転したのですが、それが後々の私の活動にとってプラスに働くことになります。
文系の大学に進学するか、理系の大学にするか、紆余曲折がありながら、最終的には東京海洋大学(旧東京水産大学)に進みます。

私は漁師の家に生まれたのですが、親から漁師になれと強要されることもなく、私自身も漁師を選ぶつもりはありませんでした。しかし、漁港や漁民、地域のために貢献していた祖父の影響もあって、「祖父が導いてくれる道だ」と大学を決めました。
大学4年生のとき、現在も活動を続けている「さかなの会」を初めて開催します。インカレとして取り組んでいた、“おしゃれなさば缶を食べよう”というコンセプトで企業にプレゼンを行う活動の一環から、私の実家で捕れた魚を食べようとなったのが、立ち上がりのきっかけです。はじめは学生を集めた単なる“家飲み”でしたが、社会に出て数年後、当時のメンバーから「また、さかなの会をやろうよ」と声をかけてもらって、活動が続いていきます。
「さかな」が自分の生きる道になる
大学院を卒業後はITシステム会社で働くことになりました。そこでの仕事は、社会的な意義があり、素晴らしい仕事でしたが、私にとっては、あまり面白いものではありませんでした。
基本的に、上から言われたことをその通りこなすことを良しとする仕事で、自発的に新しいことをやりにくかったんですね。安定を求めて選んだ就職先でしたが、小さな頃からクリエイティブな仕事をやりたかった私には、自分を押し殺すことも多かったように思います。
そのタイミングで「さかなの会」の活動が再開したのですが、それが面白くて、ライフワークとして本業以外の活動に注力していくことになりました。私の自宅でおいしいさかなを食べるだけだったところから、40人くらいの規模の飲み会に拡大し、お店を貸し切ってやるようになりました。

そこから参加者から会費を集める方式にしましたが、そうするとキャンセルが出てくるようになります。当初、キャンセルにかかる費用は自分で負担していましたが、それも違うなと思い、そのリスクをあらかじめ費用に上乗せして集めるようにしました。するとキャンセルが出なかったときに若干の利益が出るのですが、それをサイトの制作やロゴの作成といった運営費に充てていきました。
こうして、少しずつですが「さかなの会」は事業らしさを帯びながら、今の活動の原型として形づくられていきます。
大ヒットの記事執筆から開けた道
大学院を出てから7年ほどIT企業に勤務していたのですが、自分に合わない職場でそれなりに仕事をこなしていると、やはり合わない仕事が次々と来るようになります。そうして、精神面でも追い込まれるようになっていきました。
同時に、「さかなの会」の活動が自分の中で大きなウエイトを占めるようになっていきました。私にとって「さかな」は、生まれたときから身近にあった、空気のような存在です。さかなの会を通じて、ますます、さかなで人々を喜ばせたいと考えるようになりました。
しかし、会社員をしながらさかなの活動を続けていくことへの限界を感じていました。そこで、思い切って独立する道を選びました。

独立に向けては、肩書があったほうが良いと思ったのですが、自分をどのように名乗るかが悩ましいところでした。はじめは「おさかなコンサルタント」のイメージだったのですが、少し“上から目線”の印象があったので、フラットに見てもらえるようなネーミングを探していました。その中で、「コーディネータ」の言葉が目に留まり、「おさかなコーディネータ」として活動することにしました。
独立の軸となる書く仕事

「おさかなコーディネータ」として活動しはじめた頃は、“さかなを食べる”といったイベントを中心に展開していました。しかし、独立するタイミングで、BtoCだけでは絶対に稼げないことには気づいていました。自分1人で、しかもリソースがない中で稼ぐためにはBtoBの仕事を取っていかなければなりません。
そこで、さまざまな企業を回って、「何かお手伝いできませんか」と聞いて回りました。ただ、当然ですがすぐに仕事をつくれるということはなく、最初に仕事らしい仕事をしたのは、地元の新聞『上越タイムス』のコラムの執筆でした。
その後、偶然知り合った『ダイヤモンド・オンライン』の編集者の方が、私の仕事に興味を持ってくれて、記事を1本発注してくれました。実は、ダイヤモンド社の雑誌を愛読していて、その会社のメディアで記事を書くことは夢のようでした。
そして、これが大きな転機になりました。その記事が大ヒットになり、その後もダイヤモンド・オンラインから仕事をいただけるようになったのです。そうして“書く仕事”を淡々とこなすうちに、周りに影響も与えることができるようになってきました。
加えて、大きいのが「ふるさと納税」の仕事です。
もともとふるさと納税に興味があったので、そのポータルサイト(『ふるさとチョイス』)を運営するトラストバンクに、記事企画を持ち込みました。幸運なことに社長の共感を得ることができ、企画はあっさり採用されました。
そこで書いた最初の企画「【お礼の品徹底比較】プロが選ぶおすすめのうなぎ20種類の特徴まとめ」は、世の中で初めてプロが紹介するふるさと納税のコンテンツとなりました。これが爆発的なヒットとなり、地方都市への寄付額は何倍にも増えたのです。そこから、徐々にふるさと納税の返礼品を紹介する仕事も増えていきます。
コロナ禍で開けた自分自身の存在価値
独立から数年後、2020年の新型コロナウイルスの感染拡大も大きな契機となりました。
この頃は、地域系コンサルティング会社にも席を置き、地域ブランディングの調査・コンサルの仕事もしていました。この仕事は自分の勉強にもなっていたのですが、もともと独立思考が強かった私は、2年ほどの勤務を経て、再び完全フリーで仕事をするようになりました。
このタイミングは、ちょうどコロナ禍になる時期です。それまで続けていた自治体の仕事でも、生活する程度にはなんとかなります。しかし、民間の漁業の現場はこの頃本当に大変な状況で、「今は行政相手に仕事をするのではなく、もっと直接的に現場の人のために仕事をしていきたい」と思うようになりました。

また、コロナ禍によってリアルに会う活動はしにくくなり、オンラインでの接客や魚のネット通販などが求められる中で、もともとIT系だった私は、より一層ITの分野に注力すべきだと判断しました。
こうして、新型コロナ禍以降では、ふるさと納税のコンテンツづくりと、ECでの魚販売についてコンサルティングを行う仕事に、ビジネスの軸が移っていきました。
また、自分自身の仕事や生活に関するマインドも変わっていきました。ただ受けた仕事をこなしていくだけでなく、事業に対しても投資とリターンのバランスを考えられるようになりました。今ではお客様に喜んでもらえることを第一に考え、その機会も増えてきています。
本当に頑張った人が報われる世の中に
漁業の集落で生まれた私にとって、水産業に携わっている期間が長い分、一般の人が知らない業界の裏側も理解しています。そして、日本の昔からある漁業は、今大きな誤解をされています。
もともと日本がやってきた、丸々1匹の魚を食べ、たくさんの種類の魚を獲り、それを季節に応じて食べ方を変えていくことは、環境にも良いし、今でいうところの持続可能性のあることだとも自信を持って言えるものです。
しかし、マス消費やグローバル化によって欧米型の食文化、食習慣がもたらされました。その影響により、需要の少ない魚種よりも、マグロやサーモンといった需要の大きい魚種を大規模に展開したほうが儲かって良い、という考え方が浸透していきました。つまり、さまざまな魚種と共存している自然本来の状況を考えずに、「儲かる事業」のために都合の良いことばかりが正義のように語られているのです。
その中では、日本のやってきた漁業のあり方が、環境に良いものではないとされ、否定されることもあります。しかし、それは大きな間違いです。私はそれを、魚の魅力を伝える活動を通して世界中の人に広めたい。

また、ときに日本の漁師や漁法が叩かれたりしますが、その誤解を解いて、世界の人にこれからの魚のビジネスのあり方を理解いただけるようにしていきたい。国内では、今回出版した『魚ビジネス』を通して、ある程度それができたかなと思っています。次は、海外に目を向けて、その関わりを増やしていきながら、日本の漁業の文化・仕組みの良さを世界の人に届けていきたい。
そして、水産業の仕事を一生懸命に頑張っているけれど、正当に評価されない方々がいます。本当に頑張った人が報われる世の中に変えていきたい。漁師の家庭で生まれ育った人間として、それをまずは水産の業界から…と思うわけです。
すべての根本は、魚を通して、周りの人が喜んでくださることです。魚のビジネスを通して、目の前の人と向き合い、そこに広がる人たちを喜ばせることを真摯に広げていけるよう、これからも魚の魅力を伝え続けていきます。

魚ビジネス
著者:ながさき一生
定価:1738円(1580+税10%)
発行日:2023年4月21日
ISBN:9784295408192
ページ数:272ページ
サイズ:188×130(mm)
発行:クロスメディア・パブリッシング
発売:インプレス
Amazon